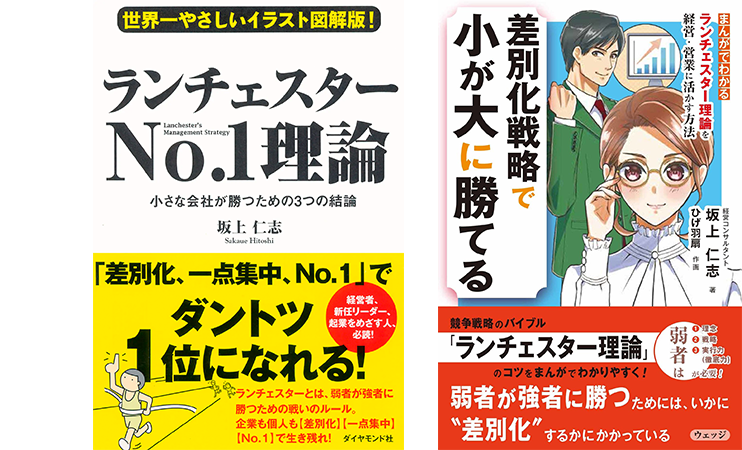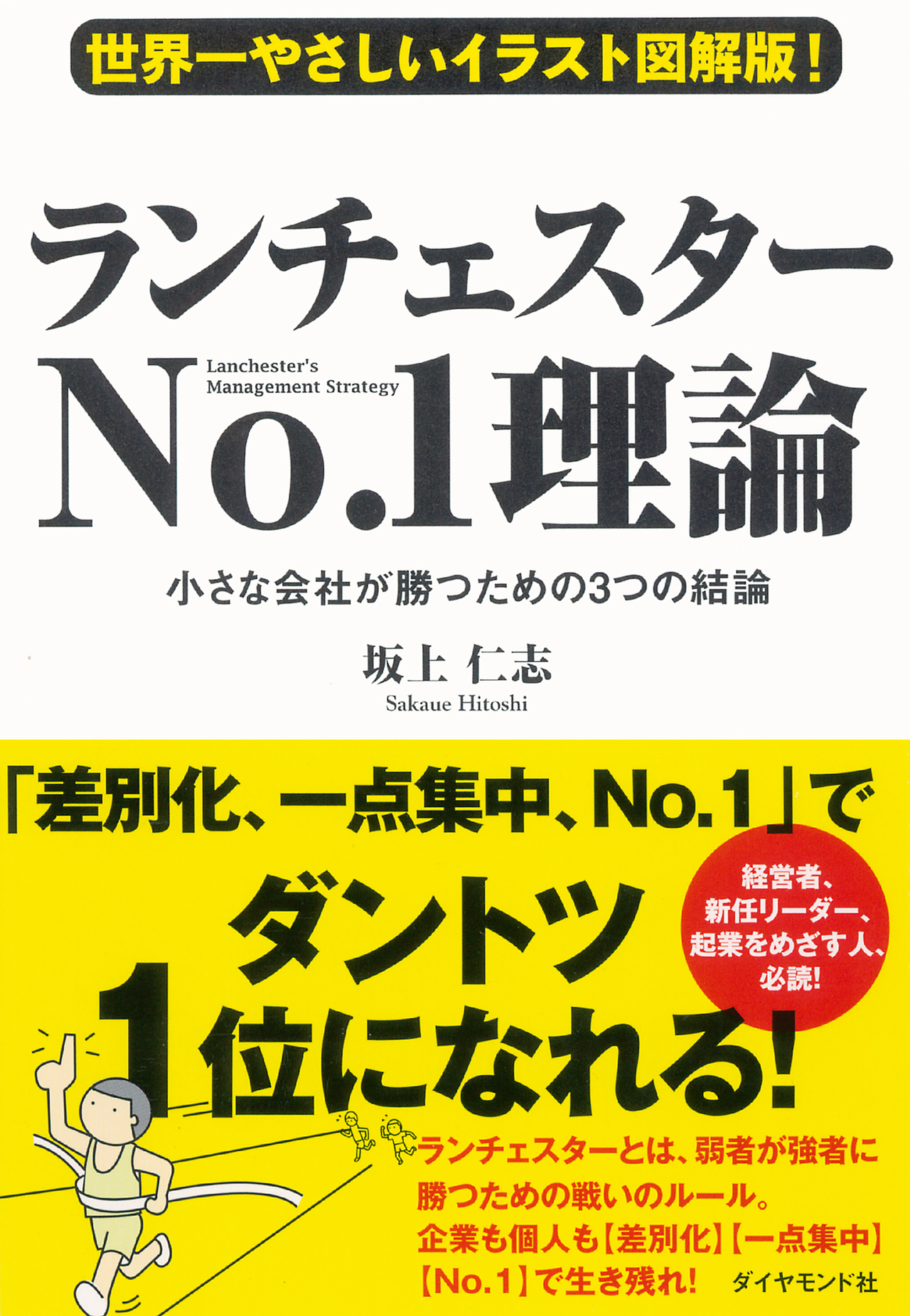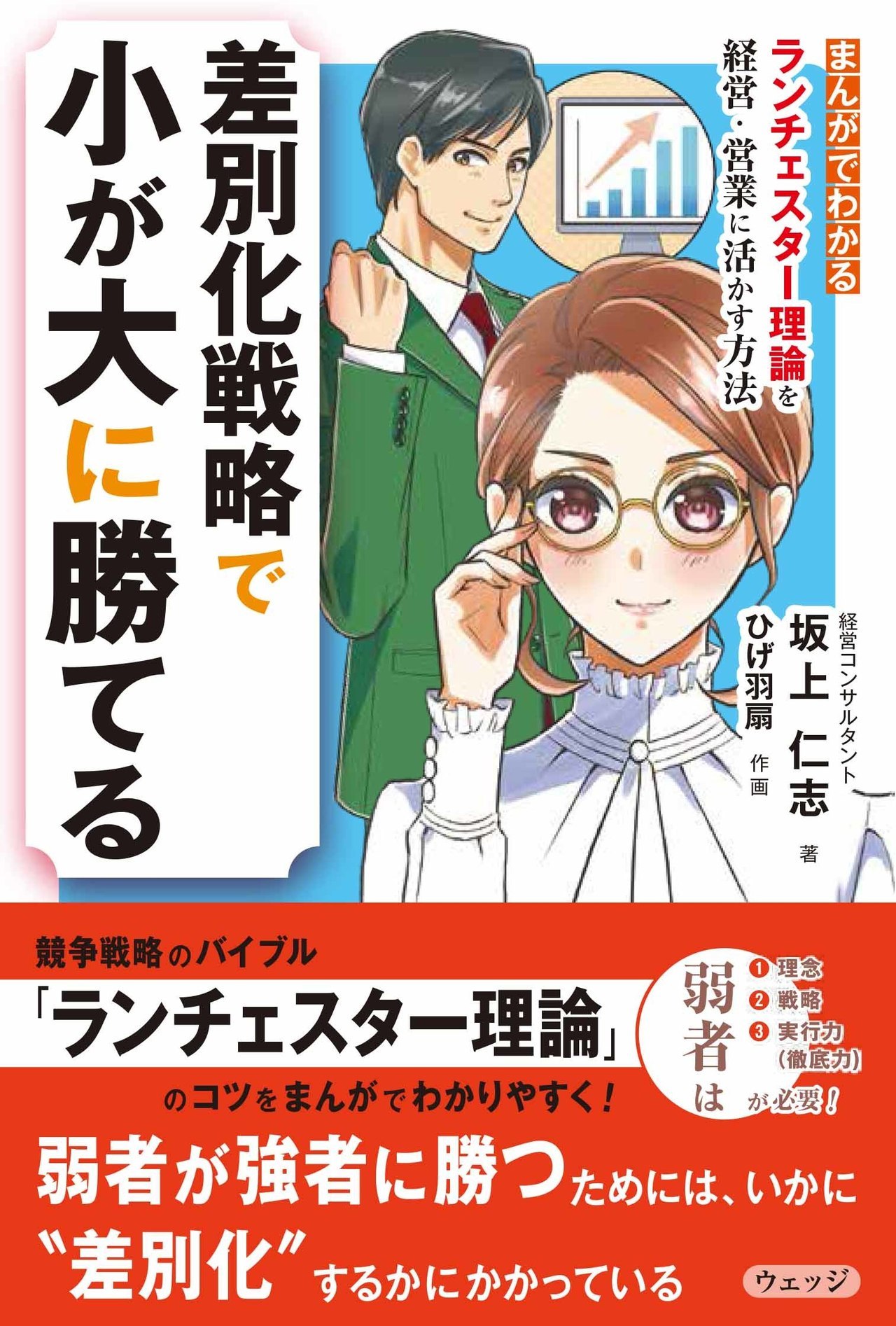↓
===================================
自らの競争力を高めるには、ベンチマーキングの手法が必要である
この手法こそグローバルな競争力を明らかにするものである
基本にある考え方は、誰かにできることは他の者にもできるというものである
最高の仕事ぶりは、自らの組織内に、
または競争相手に、あるいは別の産業に見つけることができる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
スタッフに関しても、スタッフ部門の仕事についてと同様の原則がある
いくつかの現業の仕事、できれば二つ以上の部門で実績をあげた者でなければ
スタッフに任命してはならない 現業の経験がなければ、現業に対し傲慢になる
計画するものにとっては、現業は常に単純きわまりない仕事に見える
ところが最近の組織は、ビジネススクールやロースクールを出たばかりの若者を
アナリストやプランナーとして、かなり上級のポストにつけている
その結果、彼ら自身の傲慢さと現業からの拒絶反応のために、
ほぼ確実に非生産的な存在になっている
スタッフの仕事を一生の仕事にさせてはならない 一時の仕事としなければならない
スタッフの仕事に五年から七年たずさわった後は現業に戻す
ふたたびスタッフの仕事につかせるときは、現業の仕事を五年以上こなした後にする
そうしないかぎり、やがて人形遣い、用人、黒幕となる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
スタッフ部門の効率化をはかるには、3年以内に欠勤を二分の一に減らすとか、
2年以内に市場の細分化を把握し、製品ラインの数を三分の一に減らすというように
具体的な目標と期限を定めなければならない
そのような具体的な目標だけが、スタッフ部門の生産性をあげる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大組織といえども万能ではない
組織は一時にわずかの仕事にしか取り組めない
組織構造やコミュニケーションの工夫ではどうにもならない
組織では集中力がカギである
しかも組織は変化しなければならない
変化とイノベーションの主導権をとらなければならない
そのためには、知識労働という稀有で費用のかかる資源を
成果の上がらない分野から、成果と貢献の機会のある分野へ移す必要がある
資源の浪費は許されない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
善意で山は動かない 山を動かすのはブルドーザーである
使命と計画は善意にすぎない 戦略がブルドーザーである 戦略が山を動かす
成果を求めて働くようにさせてくれるものが戦略である 戦略が意図を行動に変える
いかなる資源と人材が必要かを明らかにする
計画はつくった しかし、実際に行わないかぎり、なにも行ったことにはならない
戦略であれば、期待するものではなく、働くためのものであることがはっきりしている
戦略がうまくいかないときの鉄則は、もう一度行う、
それでもだめなら別のことを行うである
もちろん一度ではうまくいかないことが多い
そのときには、わかったことは何かを考える そうして改善する もう一度力を入れる
それでもだめならばあまり勧めたくはないが、さらにもう一度試みる
それでもだめならば、成果の出る他の戦略に移る
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
時間と資源は限られ、行うべきことは多い
例外はある 荒野で25年間汗を流して大きな成果をあげる人がいる
ただし稀である ほとんどの場合、荒野にしがみつく人の多くは屍しか残せない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
意思決定を行動に変えるには、いくつかの問いに答えなければならない
誰がこの意思決定を知らなければならないのか、いかなる行動が必要か、
だれがその行動をとるか 行動する役目の者が行動できるためには、
その行動はいかなるものでなければならないか
意思決定を実行に移すための行動は、
その行動をとるべき者の能力に見合っていなければならない
このことは、行動をとる者が、それまでの行動や習慣や態度を
変えなければならないとき、とくに重要な意味を持つ
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
意思決定が成果をあげるには、満たすべき要件を明確にしておく必要がある
要件が何かを明らかにしなければならない
要件を明確かつ簡潔にするほど、意思決定は成果をあげるものとなり
達成しようとするものを達成するようになる
逆に、いかに優れた意思決定に見えようとも、
要件が曖昧であれば成果をあげられないことは必定である
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
三人の石切り工の話がある
何をしているのかを聞かれて、それぞれが
「暮らしを立てている」「石切りの仕事をしている」「教会を建てている」と答えた
第三の男こそ真のマネージャーである
第一の男は、仕事で何を得ようとしているのかを知っており、事実それを得ている
一日の報酬に対し一日の仕事をする だがマネージャーではない
将来もマネージャーにはならない
問題は第二の男である 熟練した専門能力は不可欠である
たしかに組織は、最高の技能を要求しなければ二流の存在になる
しかしスペシャリストは、たんに石を磨き脚柱を集めているにすぎなくとも
重大なことをしていると錯覚しがちである
専門能力の重要性は強調しなければならない
だが、それは全体のニーズとの関連においてでなければならない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
人事は大きな賭けである しかし、それぞれの強みに焦点を合わせることによって
合理的な賭けにすることはできる 優れた人事は人の強みを生かす
できることを中心に据えて、移動を行い昇進させる
人事において重要なことは、人の弱みを最小限に抑えることではなく、
人の強みを最大限に発揮させることである
大きな強みをもつ者は、ほとんど常に大きな弱みをもつ 山あるところに谷がある
申し分のない人間などありえない
そもそも、何について申し分がないかが問題である
無難にこなす能力ではなく、一つの分野で抜きんでた能力を探さなければならない
人が抜きんでることのできるものは一つか、せいぜい二つか三つの分野である
よくできるはずのことを見つけ、実際にそれを行わせなければならない
弱みそれ自体が大きな意味を持つ領域は一つしかない
真摯さの欠如である 真摯さそれ自体だけでは何ものももたらさない
しかし、それがなければ他のあらゆるものが台無しとなる
真摯さの欠如だけは、あってはならない絶対の基準である
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
厳しい競争社会にあって40代で燃え尽きる人たちが増えている
彼らはもうこれ以上の地位がないことを悟る
そのとき仕事がすべてであれば、問題が生ずる したがって、若いうちに非競争的な
生活、コミュニティ、夢中になれるものを手に入れておく必要がある
それらのものが仕事とは関係なく貢献と自己実現の場を与える
仕事や人生で挫折がないことはありえない 昇進し損ねた42歳のエンジニアがいる
現在の仕事ではうまくいかないことを悟っている
だが、もう一つの仕事 たとえば教会の会計責任者としては立派な仕事をしている
これからも立派な仕事をしていける
あるいは、家庭が壊れるかもしれない しかし、自分のコミュニティがある
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
強みと同じように、仕事のやり方も人それぞれである
あるものは読んで学び、あるものは聞いて学ぶ
読み手が聞き手になることはあまりない 逆もない
仕事のやり方の違いは他にもある
人と働いた方がよいか それであれば、部下としてか、同僚としてか、上司としてか
働く場所としては、しっかりとした組織のほうがよいか
仕事には何らかのプレッシャーがあったほうがよいか、ないほうがよいか
もう一つ 自らをマネジメントするには、
自らにとって価値あるものは何かを考えなければならない
自らが価値ありとするものと自らの強みは一致するか、
あるいは、少なくとも相反することはないか
両者が合わないとき、優先すべきは価値観のほうである
価値観に反する仕事は人を堕落させる 強みすら台無しにする
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
知識労働者には特有の問題がある 若くしてやる気を失うことがある
40代での燃え尽き現象は、仕事のストレスによるものではない 仕事への飽きからくる
ある組織で士気の低下を調べたところ、
「仕事が大切なことは承知している 気に入ってもいる 担当して10年になる
誇りにもしている だが、その仕事は眠っていてもできる
わくわくしない 飽きた 出勤も楽しくない」との類の答えが多かったという
定期異動では解決にならない すでに一流の専門家である
必要とするものは意義ある人生である
地元の中学で理科と数学を教えたところ、仕事まで生き生きとするようになったという
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
組織は人を変える 否応なしに変える 成長させたり、逆にいじけさせたりする
人を育てることについて、われわれは何を知っているか かなりのことを知っている
とくに、何を行うべきでないかについてよく知っている
行うべきでないことの方が、行うべきことよりもわかりやすい
第一に、不得意なことで何かを行わせてはならない
礼儀、態度、スキル、知識は学ぶことができる だが個性を変えることはできない
第二に、近視眼的に育ててはならない 身につけさせるべきスキルはある
だが人を育てるということは、それ以上のことである
キャリアと人生に関わることである 仕事は人生の目標にあわせなければならない
第三に、エリート扱いしてはならない 重要なことは実力であって見込みではない
要求は厳しくしなければならない
人材の育成にあたっては、つよみに焦点を合わせなければならない
そのうえで要求を厳しくしなければならない
そして、時間をかけて丁寧に評価しなければならない
向かい合って、約束はこうだった、この一年どうだったか、
何をうまくやれたか、と聞かなければならない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
間違いや失敗をしたことのない者だけは信用してはならない
そのような者は、無難なこと、安全なこと、つまらないことにしか手をつけない
人はすぐれているほど多くの間違いをおかす 優れているほど新しいことを行うからである
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自らの貢献は何であるべきかとの問いに答えを出すには、
三つの要因を考えなければならない
第一に、何が求められているかである
第二に、自らの強み、仕事の仕方、価値観をもって何に最も大きな貢献をなしうるかである
そして第三に、世の中に違いをもたらすためには、いかなる成果を生み出すかである
ここから、行うべきこと、始めるべきこと、始め方、目標、期限などの
アクションプランを明らかにすることができるようになる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
優秀な若者は強い上司をまねたがる
したがって、腐った強いものほど組織を腐らせる者はいない
これは、それだけで人を失格にする唯一の弱みである
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自己啓発は貢献に集中して取り組むかどうかにかかっている
自らの貢献を問うことは、いかなる自己啓発が必要か、
いかなる知識とスキルを身につけるか、いかなる強みを仕事に適応するか
いかなる基準をもって自らの基準とするかを考えることにつながる
人は自らに課す要求に応じて成長する
自らが成果とみなすものに従って成長する
自らに少ししか求めなければ成長しない
多くを求めるならば、なにも達成しない者と同じ努力で巨人に成長する
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
人は、誇れるものを成し遂げることによって誇りを持つことができる
さもなければ、偽りの誇りであって心を腐らせる
人は何かを成し遂げたとき、自己実現する 仕事が重要なとき、自らを重要と感じる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
人が働くのは、精神的、心理的に必要だからだけではない
人は何かを、しかもかなり多くの何かを成し遂げることを欲する
自らの得意なことで何かを成し遂げることを欲する
したがって、働く意欲のベースとなるものが能力である
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
トップたる者は、自らの優先順位を部下に知ってもらわらなければならない
トップが何を考えているかがわからなくなったとき、組織は転落する
自らが力を入れていることを知ってもらい、
部下たちが力を入れていることを知らなければならない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
成功は常に、その成功をもたらした行動を陳腐化する
新しい現実を作りだす 新しい問題を作りだす
成功しているマネジメントが、事業が何かを問い直すことは容易ではない
議論の余地はないとする ケチをつけることを好まず、ボートを揺らすことを好まない
しかし、成功しているときに自らの事業を問わないマネジメントは、
つまるところ傲慢であって、怠慢である 成功が失敗に終わる日は近い
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
起業家戦略は4つある
総力戦略、二番手戦略、価格戦略、ニッチ戦略である
これらは互いに相容れないものではない
二つあるいは三つの戦略を組み合わせて一つの戦略にすることもできる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
総力戦略とは、南北戦争における南軍騎兵隊の勝利の方程式である
起業家は、この戦略によってトップの地位を得ようとする
得るものが大きい代わりに、リスクも大きい
失敗は許されず、チャンスは一度しかない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
二番手戦略では、起業家は新しい製品やサービスを創造しない
誰かが創造したものを改善する その一つが模倣である
だが顧客のニーズと欲求に、よりよく応えられるようにするがゆえに創造的である
こうして顧客の欲するものの創造に成功するならば、
リーダーの地位を獲得し、市場を支配するようになる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
柔道の名人は相手の得意技を熟知している
相手がその技を使うことを察知する
その技がいかなる隙を生むかを予期する
その隙をつくことによって相手を倒す
事業において行動はパターン化する
事業における柔道家は、リーダーの地位にある者の得意技に隙を見つける
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
起業家戦略には、製品やサービスのイノベーションが必要である
ところがここに、価格のつけ方がイノベーションであるという起業家戦略がある
製品やサービスは昔からあるものでよい
価格のつけ方によって、効用、価値、経済的な特性を変化させる
新しい価値を生み、新しい顧客を生む しかし、製品やサービスそのものは変えない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ニッチ戦略は、小さなニッチ(隙間、適所)での独占を目指す
ニッチ戦略の一つである関所戦略では、プロセスの一部として不可欠の部分を探す
プロセス全体から見れば、問題にならないコストのものである
しかも、あまりに売り上げが小さいために、競争相手が入ってくる余地がない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ニッチ戦略の一つに専門技術戦略がある
大手自動車メーカーの名前を知らない人はいない
ところが、電気系統システムを供給する部品メーカーの名前を知っている人はほとんどいない
それら有名でない部品メーカーが専門技術のニッチを占拠している
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ニッチ戦略の一つに、
競争相手が現れるほど大きくはない市場を狙う専門市場戦略がある
あらゆるニッチ戦略に共通する弱点が永続性の欠如である
第一が、技術上の変化に足をすくわれることがある
第二が、専門市場が大衆市場に変わることである
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自己啓発とは、能力を習得するだけでなく、人として大きくなることである
責任を重視することによって、より大きな自分が見えるようになる
うぬぼれやプライドではない
誇りと自信である
一度身につけてしまえば失うことのない何かである
目指すべきは、外なる成長であり、内なる成長である
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
人の育成にあたって最も有効な方法は先生役をしてもらうことである
教えることほど学べることはない
先生役を頼むことは最高の評価である
営業マンであれ赤十字のボランティアであれ、
どうして成績がよいのか話してくださいと頼まれることほど、うれしいことはない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
経営者のほとんどは、あらゆる資源のうち人が最も活用されておらず、
その能力も開発されていないことを知っている
だが現実には、人のマネジメントに関するアプローチの多くが、
人を資源ではなく、問題、雑事、費用として扱っている
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
企業家が金に無頓着ということはあまりない
多くの場合、貪欲である
そのため利益を重視する
しかし、それはベンチャーとしては間違った態度である
利益は結果としてもたらされるものであって、最初に考えるべきものではない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自らを存続させられない組織は失敗である
したがって、明日のマネジメントを担うべき人材を今日用意しておかなければならない
人的資源を更新していかなければならない
確実に高度化していかなければならない
ビジョン、能力、業績において、今日の水準を維持しているだけの組織は、
適応能力を失ったというべきである
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この世において唯一確実なものは変化である
自らを変革できない組織は、明日の変化の中で生き残ることはできない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
実現すべき成果はだれにとっても明白である
企業においては経営上の業績である
病院においては患者の治癒である
成果がなんであるべきかが混乱している状態では、成果は期待しえない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
明確かつ焦点の定まった共通の使命だけが組織を一体化し、成果をあげさせる
焦点の定まった明確な使命がなければ、組織は組織としての信頼性をただちに失う
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ベンチャーが成功するのは、多くの場合、
思いもしなかった市場において、
思いもしなかった顧客が、
思いもしなかった目的のために買ってくれることによる
この事実を認識し、
予期せぬ市場を利用できるよう自らを組織しておかないかぎり、
すなわち、あくまでも市場志向、市場中心でないかぎり、
ベンチャーは競争相手のために機会をつくっただけに終わる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
コスト削減には常に努めなければならない
事業は人体と同じである
健康な生活を送っていても調子は悪くなる コスト削減は常に必要である
通常、コスト削減は、
どのようにしてこの活動の効率を高めるかを考えることから始まる
これは間違いである
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
あらゆる組織が三つの領域での貢献を必要とする
すなわち、成果、価値、人材育成である
これらすべてにおいて貢献がなされなければ、組織は腐り、いずれ死ぬ
したがって、この三つの領域における貢献を、
あらゆる仕事に組み込んでおかなければならない
貢献に焦点を合わせるということは、責任をもって成果をあげるということである
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
仕事に焦点を絞らなければならない
仕事が可能でなければならない
仕事がすべてではないが第一である
たしかに、働くことの他の側面において不満足であれば、
もっとも働きがいのある仕事でさえ台なしになる
ソースがまずければ、最高の肉も台無しになる
だが、そもそも仕事そのものにやりがいがなければ、どうにもならない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
強みに集中せよとの格言は常に正しい
組織は多角化していないほどマネジメントがしやすい
単純であれば明快である
全員が自らの仕事を理解し、自らの仕事と全体の業績との関係を知る
活動を集中する
期待を明確に規定することもできるし、成果を評価することもできる
問題も少なくなる
複雑になれば、原因を突き止めることが難しくなる
複雑さはコミュニケーションの問題を起こす
マネジメントの階層が増え、書類と手続きが増え、会議が多くなり、意思決定が遅れる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
好きなことをするというだけでは自由になれない
勝手気ままにすぎない
いかなる成果もあげられない
貢献もなしえない
自らのなすべき貢献は何かとの問いからスタートするとき、人は自由になる
責任をもつがゆえに自由になる
成功のカギは責任である
自らが責任をもつことである
あらゆることがそこから始まる
大事なのは地位ではなく責任である
責任ある存在になるということは、真剣に仕事に取り組むということであり、
仕事にふさわしく成長する必要を認識するということである
貢献に集中し成果をあげる、成功のカギは責任である
努力ではない
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自らの貢献を問うことは、可能性を追求することである
そう考えるならば、多くの仕事において優秀な成績とされているものの多くが、
その膨大な可能性からすればあまりに貢献の小さなものであることが分かる
いかなる貢献をなしうるかを自らに問わなければ、
目標を低く設定してしまうばかりでなく、間違った目標を設定することになる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
企業の使命と目的を定義する際の出発点は一つしかない
顧客である
顧客を満足させることが企業の使命であり目的である
われわれの事業は何かとの問いは、
企業を外部、すなわち顧客と市場の観点から見て、初めて答えることができる
ドラッカー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−