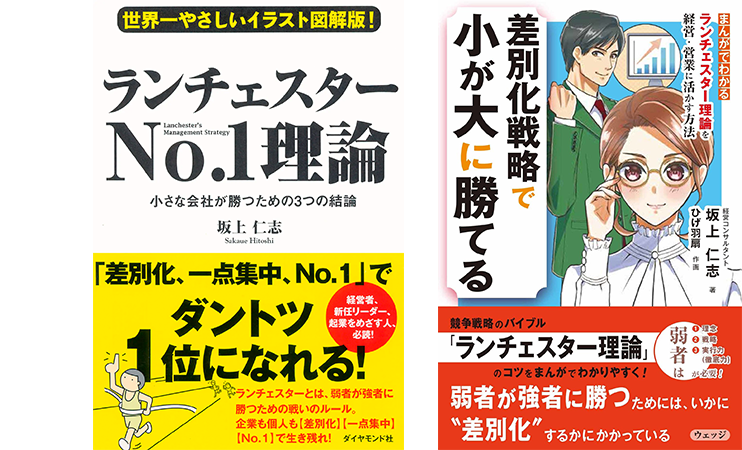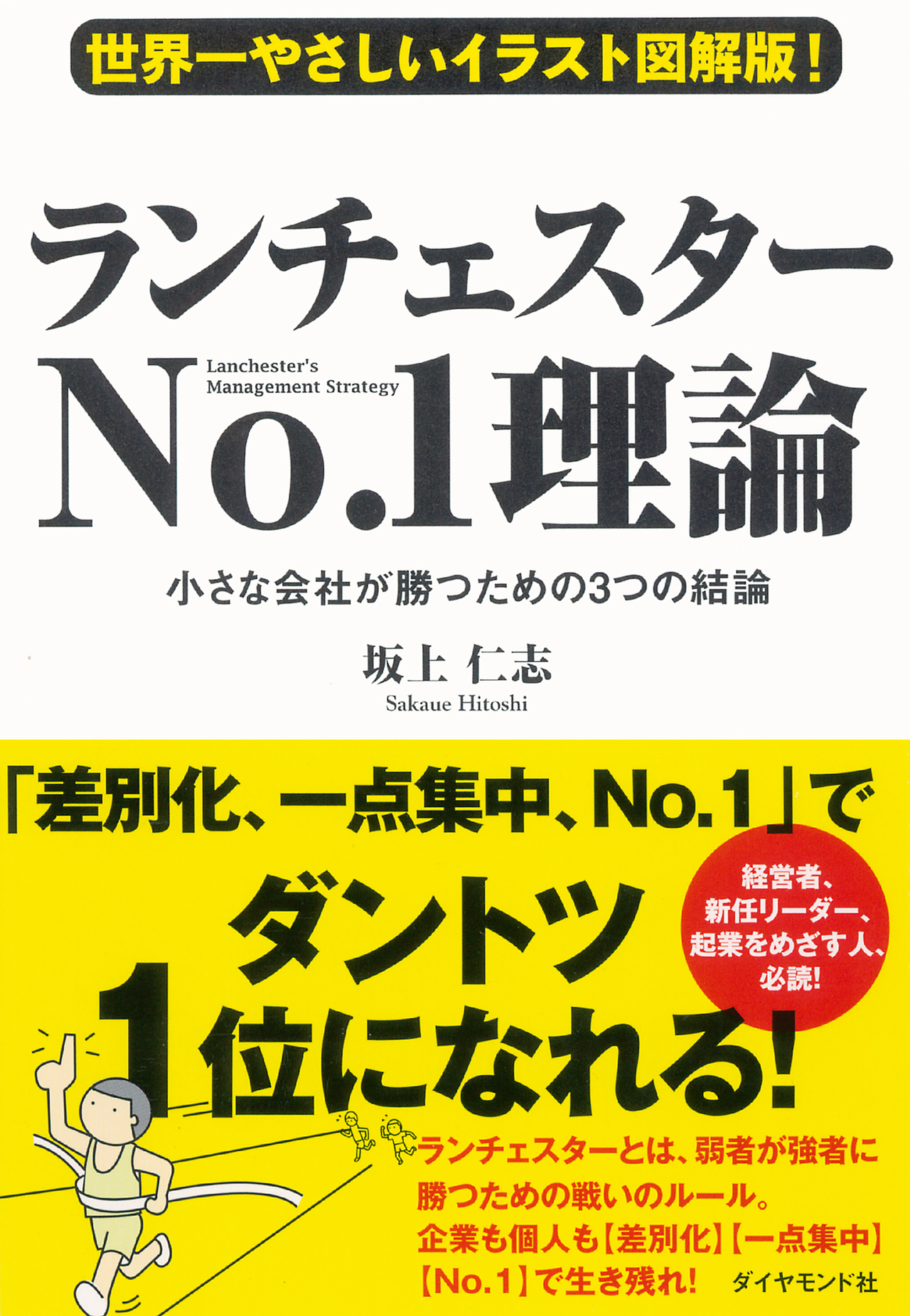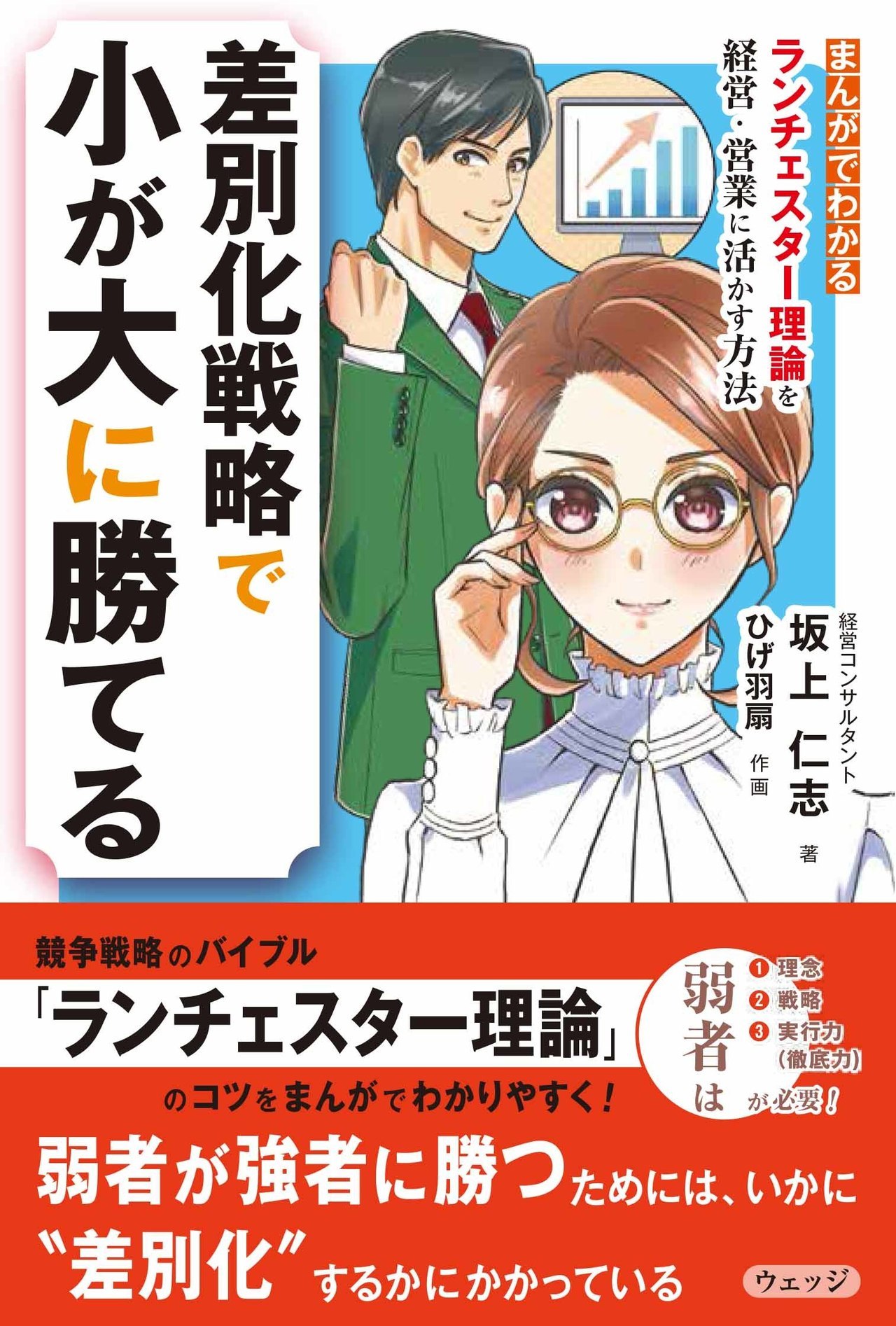ランチェスター戦略 ランチェスター法則とは?
・
ランチェスター戦略とは、弱者が強者に勝つルール
「あなたがランチェスター戦略を学ばなければ、他の誰かが学んでしまう。
その人と対決したらあなたは負ける」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 ランチェスター戦略とは、弱者が強者に勝つためのルール
2 ランチェスター第一法則は、弱者の戦略
3 ランチェスター第二法則は、強者の戦略
4 ランチェスター法則に学ぶ! 3つの戦い方のセオリー
5 大企業=強者、小さい会社=弱者というわけではない
弱者と強者の定義
6 弱者と強者では戦い方が全く違う! 弱者と強者の5大戦法をチェック
7 弱者の基本戦略は、他と差別化すること
8【ランチェスター戦略の結論】
9 ランチェスター戦略 NO1の定義
10 ランチェスター戦略 NO1のなりかた
11 ランチェスター戦略 占有率=シェアの考え方はなぜ必要か?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 ランチェスター戦略とは、弱者が強者に勝つためのルール
ランチェスター戦略とは、
一言でいうと弱者が強者に勝つための戦い方のルールです。
ランチェスター戦略は、
①ランチェスター法則と②ランチェスター戦略方程式の2つの考え方から、
故田岡信夫氏が体系化した経営活動における販売戦略・競争戦略のことです。
ランチェスター戦略のもとになったランチェスター法則とは、
1868年ロンドン生まれのフレドリック・W・ランチェスターが、
第一次世界大戦の時に導き出した戦い方の法則です。
「戦闘力は、兵力の質と量の積」で表されます。
それが、第二次世界大戦の際に、
ランチェスター戦略方程式として進化発展しました。
つまり、ランチェスター戦略とは、
戦争における戦い方の法則をビジネスに応用したものです。
市場原理に基づいた競争に、
企業がどう戦ってゆけばよいのかを示す、戦い方のルールです。
将棋や囲碁に勝つための定石があるように、
経営にも目に見えない勝つための法則、原理原則があるのです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2 ランチェスター第一法則は、弱者の戦略
ランチェスター法則は、とてもシンプルです。
たった二つの項目(質と量)により、
たった二つの法則(第一法則と第二法則)でできています。
このランチェスター第一法則とランチェスター第二法則は、
全く逆の状況を仮定しています。
ランチェスター第一法則は、
局地戦、接近戦、一騎打ち(1対1の戦い)
の場合に当てはまる戦闘力の法則です。
互いに刀を持って戦うような、極地で接近して一騎打ちをする場合は、
戦闘力=武器効率(質)×兵力数(量)となります。
A軍(5名)B軍(3名)で、
刀の武器効率(質)が同じなら、
戦闘力は兵力数(量)に比例するので
A軍(5名)が5-3=2名を残して勝ちます。
ランチェスター第一法則
戦闘力=E*兵力数 (質*量)
E=武器効率をあらわす
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3 ランチェスター第二法則は、強者の戦略
ランチェスター第二法則とは、
広域戦、遠隔戦、確率戦(集団対集団の戦い)
の場合に当てはまる戦闘力の法則です。
つまり、互いにマシンガンやミサイルを持って戦うような、
広域で、遠隔地で、多人数どうしで戦う場合では、
戦闘力=武器効率(質)*兵力数(量)の二乗となります。
A軍(5名)B軍(3名)で、
マシンガンの武器効率(質)が同じなら、
戦闘力は兵力数(量)の二乗に比例するので
A軍(5名)が5-1=4名を残して勝ちます。
ここでも結論として兵力数が多い方が勝つ、
それも数が多い方が圧倒的に勝つことになります。
つまり、数が少ないほうは、ランチェスター第二法則が適用される、
広域戦、遠隔戦、確率戦(週団体集団の戦い)では戦ってはならない。
なぜなら、戦えばコテンパンにやられてしまうからです。
ココがすごく重要なところです
戦闘力=E*兵力数2(二乗) (質*量2)
広域戦、遠隔戦、確率戦の法則=強者の法則
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4 ランチェスター法則に学ぶ! 3つの戦い方のセオリー
ここまでお話しした、
ランチェスター第一法則、第二法則からわかることは、以下です。
①数の多い方が常に有利、数の少ない方は常に不利、勝負は力関係で決まる
②数が少ない方は、第一法則に従った戦い方をすること
③数の多い方は、第二法則に従った戦い方をすること
ランチェスター第一法則は、
局地戦、接近戦、一騎打ちの場合、
つまり、狭い、近い、1対1の戦いに当てはまり、
弱者の戦い方であるということです。
ランチェスター第二法則は、
広域戦、遠隔戦、確率戦の場合、
つまり、広い、遠い、集団対集団の戦いに当てはまり、
強者の戦いであるということです。
ここで大切なことは、
ランチェスター第二法則が適用される広域戦、遠隔戦、確率戦の場合は、
兵力数が二乗になるので数の多い方が圧倒的に有利になってしまうので、
弱者は第二法則で戦ってはならない、
第一法則で戦う、ということです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5 大企業=強者、小さい会社=弱者というわけではない
弱者と強者の定義はなにか?
ふつうは大きな会社が強者、小さな会社が弱者と考えますが、
ランチェスター戦略では違います。
強者とは、企業同士が競合する局面において、市場占拠率1位の企業のこと。
弱者とは、同じ競合する局面において、
市場占拠率1位以外のすべての企業のことです。
つまり、ランチェスター戦略では、
競合局面における市場占拠率(シェア)によって、
強者と弱者を区別するのです。
競合局面とは、
①地域(どこの)、
②顧客(だれに)、
③商品(何を)、
④流通(どう)、
という4つの視点です。
このように細分化した切り口(視点)で考えることが大切です。
たとえば、ある地域のシェアだけで見れば、
小さな会社が1位(強者)で、大企業が2位(弱者)の場合もあります。
企業規模の大小だけが重要ではない。
ここが、ランチェスター戦略が中小企業に勇気を与えてくれるところです
したがって、大企業が必ずしも強者とはならない
例えば、キリンビールも北海道というエリアでは弱者であり
サッポロビールが強者となるのです
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
6 弱者と強者では戦い方が全く違う! 弱者と強者の5大戦法をチェック
ランチェスター戦略に従えば、
弱者(2位以下)と強者(1位)では戦い方が、
全く180度違うことになります。
そして、それぞれの基本戦略はこれです。
弱者の基本戦略は、
【差別化】戦略=強者とは違う差別化した戦略をとること
強者の基本戦略は、
【ミート】戦略=弱者の戦略に合わせて同じことをすることです。
弱者も強者もそれぞれ、この基本戦略をベースとして、
次の5大戦法があります。
弱者は、①局地戦、②接近戦、③一騎打ち、④一点集中、⑤陽動戦
強者は、①広域戦、②遠隔戦、③確率戦、④総合戦、⑤誘導戦となります。
中小企業の90%以上は弱者(2位以下)でしょう。
ですから、ランチェスター第一法則に従って【差別化】戦略をしたうえで、
①局地戦、②接近戦、③一騎打ち、④一点集中、⑤陽動戦の戦法をとることです。
ランチェスター第二法則が適用される広域戦で戦うと、
戦闘力が兵力数の二乗に比例するので
大きな損害を受けることになってしまうからです。
局地戦、接近戦、一騎打ちの法則=弱者の法則
弱者の戦略=差別化戦略
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
7 弱者の基本戦略は、他と差別化すること
差別化の視点は、マーケティングの4P+サービス+地域の6つあります。
①製品(Product)=一つの商品に機能を足す、引く、分けるなど
②価格(Proce)=3つ買うと1つ無料!(お土産屋さんでよくあります)
③流通(Place)=直接販売と間接販売、WEBの組み合わせを工夫する
④プロモーション(Promotion)=販売促進のメッセージの工夫(わが社だけです)
⑤サービス=アフターサービスをつける、メンテナンス無料など
⑥地域=半径30分以内の地域だけ対応(00町を担当しています)
弱者が差別化をする時には、これらを組み合わせてください。
他社より価格を1円安くしただけでは差別化になりません。
できたら3つ以上組み合わせることです。
たとえば、製品を二つ組み合わせて、価格を少し安くして、
アフターサービスをつけたものを、地域限定、期間限定で売る
というような組み合わせの差別化戦略です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
8【ランチェスター戦略の結論】
① NO1主義
有利な立場はNO1だけ=ランチェスター戦略の結論
だから、小さい市場、狭い地域、小さな製品、
なんでもいいから小さなところで圧倒的なNO1を作ることが、
経営を有利にする
NO1でなければ意味がない、
NO1になると利益が上がり、
ブランドになる
② 一点集中主義
これこそが弱者の戦略! ランチェスター戦略
手を広げない、
やらなくてもいいことをしない、
力を分散させない
③ 勝ちやすきに勝つ
ランチェスター戦略の真髄
下位を攻撃目標とし、
上位は競争目標として区別する
攻撃目標と競争目標を混同しない
上位に戦いを挑まない
ランチェスター戦略の結論はこの3つ
① NO1主義
② 一点集中主義
③ 勝ちやすきに勝つ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
9:ランチェスター戦略 NO1の定義
ランチェスター戦略でいう、NO1とはなにか?
NO1とは競争局面において1位でかつ、
2位を「射程距離」圏外に引き離しているものです
「射程距離」とは戦いを挑める距離をあらわすものであり
局地戦、単品での勝負では・・・・・・・・・・・3:1
広域戦、全社、全品目の勝負では・・・・・√3:1
これは逆転されないシェアを理解する為の数値目標となる
これが、ランチェスター戦略での射程距離理論となります
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
10:ランチェスター戦略 NO1のなりかた
ランチェスター戦略ではNO1になり方があるといいます
弱者は、地域 → 得意先 → 商品
強者は、商品 → 得意先 → 地域
の順でNO1になっていく、
これの順番を間違えないことがランチェスター戦略では重要です
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
11:ランチェスター戦略 占有率=シェアの考え方はなぜ必要か?
ランチェスター戦略ではシェアの考え方を重視する、その理由は
① 勝ち目のある市場を選び
② 競合との力関係を知る
ことで、競争を優位に進めるため
ランチェスター戦略のシンボル数値=75:40:25
75:上限目標、独占
40:相対的安定値、安全圏
25:下限目標、
中小企業は小さな市場で25%を目標にする
そして、次に40%をとることを目標に!
小さなNO1シェアを積み上げることが大切です
ビジネスにも勝ち方のルール、原理原則があります
その勝ち方をランチェスター戦略から学んでください
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
経営理念とは何か?
3現主義(三現主義)
5W2H 意味
PREP法
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−